一人ひとりの生きざまが胸に迫る(震災取材ブログ)
@東京
「巨大災害が残したものは何か」。そんな疑問への答えを求め、阪神大震災の被災者へのインタビューを続けてきた市民グループが11日、14冊目となる記録集を発行する。阪神を経験した8人のほか、東日本大震災で家を失うなどした3人の声が初めて盛り込まれた。過酷な体験を通じた一人ひとりの思いや、編集スタッフの独自の視点が映し出されたそれぞれの言葉が印象的な内容だ。
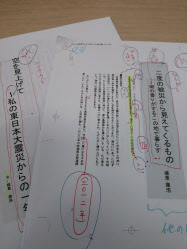
首都圏の災害ボランティアでつくる「A-yan Tokyo(えーやん とうきょう)」がまとめた冊子「震災が残したもの14」。
1995年の阪神大震災の被災地に駆け付けた若者らが、それぞれの生活に戻った後も「震災を忘れないように」と、インタビュー集を年1回のペースで出版。火災で自宅を失い、震災直後は薄く小さかった日記の文字が次第に大きく濃くなり、避難所で知り合った仲間との交流を続ける女性が「一人になった時はふさぎこんでしまう」と打ち明けるなど、ありのままの姿を描いてきた。
復興住宅に入居する被災者がコミュニティーになじめないまま暮らすなど、時間の経過とともに新たに生じる被災地の現実を前に、当初の目標だった10年を過ぎても、被災者と向き合うインタビューは継続してきた。
大学生だった結成当時から参加する千葉市の耳鼻科医、植草康浩さん(45)は昨年、宮城県石巻市の病院に勤務する女性看護師(28)の声に耳を傾け、言葉をつむいだ。宮城県で最大震度6強を記録した2003年の地震で家が損壊し、仮設住宅暮らしを経験した女性は、新潟県中越地震などで災害ボランティアの立場に回る。東日本大震災では津波で自宅が浸水し、病院に寝泊まりしながら、医療の最前線を支えたという。
2度の被災を経験した女性は植草さんに次のような心情を口にする。
――「当たり前」の幸せを感じています。今、目の前にある現実は、当たり前ではない。この毎日を過ごしていけることが幸せなんだって、改めて思うことができた」「(03年の)地震のことを覚えている人は少ないと思う。でも私は日にちも時間も忘れない。あの時どんなことが起きて、私が何を感じていたか、ひとつひとつを大切にしたい。いろんなことが風化していくことが怖い」
これまで国内で起きた大規模災害の直後にボランティアとして被災地入りを重ねてきた植草さんだが、東日本大震災では現地へ向かう仲間の後方支援などの作業に従事した。震災の約1年前にがんを患い、親族からは胸中を見透かすかのように「今は(被災地に)行かないでね。昔の体とは違うから」と諭されたという。
被災者に長年、寄り添い、医療現場で働き続ける植草さんは力を込める。「自分にとって震災が残したものとは『一日一日を、そして、家族を大切にして生きる』というものだった。大きな病という転機を経て、その気持ちを一段と強くしている。冊子を通じて、そんな思いも伝えたい」
自費出版となる「震災が残したもの14」は400部を発行予定。第1作~13作までをセットにして東北の図書館などに寄贈する計画も進んでいる。冊子に登場する被災者一人ひとり、冊子づくりにかかわる一人ひとりの生きざまが胸に迫る。
◇
冊子に関する問い合わせは「A-yan Tokyo」の白井信光編集長にメールで。アドレスはa_yantokyo@hotmail.co.jp
(西島広敦)













